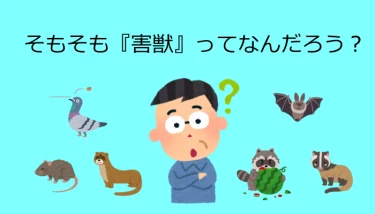床下でカリカリ音がする原因とは?
床下からカリカリと音がする場合だと、主に次のような原因が考えられます。
- 湿気や温度の変化による木材の収縮や膨張
- 建物の地盤沈下や揺れによる変形
- 害虫や小動物などの活動音
なので、一番最初に判別するべきは『その音に生命を感じるかどうか』です。
『生命を感じるか』なんて言うと馬鹿にしているのかと思われるかもしれません。
でも、建材の収縮膨張や地盤沈下などの場合、確かに音はしますが生き物の活動が原因ではないため、生き物の気配を感じることがありません。
当然ですね。そこに意志などはないのですから。
でも、害虫にしろ害獣にしろなにがしかの生命体が原因である場合は、音が不規則になったり音に強弱が出たり、とかく『気配』を伝えてきます。
なので、『その音に生命を感じるかどうか』というのはわりと重要な判断基準になったりするんです。
そして、そんな大雑把な判断でもしておくことが重要だったりします。
なぜなら、建材の収縮膨張や地盤沈下などが原因の音の場合は建築業者が相談先になりますし、害虫が害獣に住みつかれたっぽいならば、相談するべきは駆除業者になるからです。
なので、床下からカリカリ音がする……そんなときは、まずはこの『その音に生命を感じるかどうか』に注目してみましょう。
カリカリ音を聞いたら、どのような対処が必要?
先ほども解説したように、まず最初にするべきは『原因の特定』です。
これは素人なりにでも、自分である程度は判断しておくべきです。
理由は、問題を解決るための『相談先が変わるから』です。
いずれの原因にせよ、きちんとした特定は専門家に相談して知恵を借りるべきですが、相談する専門家を建築業者にするのか駆除業者にするのかを決めることができるので、無駄骨を折らずに済む確率が高くなるので自分なりにやっておくのがベターなわけです。
そして、原因にアタリをつけて専門家に相談したら、専門家に対処を依頼するのが一番無難です。
補修にしても駆除にしても、スキルのない人間が見よう見まねでやってもお金と時間を無駄にしてもしまう可能性が高いので、自分自身がその道のプロだと言い切れない人は専門家に対処を依頼するのがもっとも確実でもっともお金をかけずに済む方法だと思っていただいて間違いないでしょう。
害獣駆除が必要になったときの行動手順 1、まず落ち着く どうしようどうしようと焦ってしまうと判断を誤まりますので注意が必要です。 基本的に害獣駆除は自分では行えません(素人が根本的に解決することは難しい)ので、業者への依頼や役所([…]
床下でカリカリと音を立てる動物の種類と特徴
基本的に床下に潜り込むタイプの動物は、すべて対象になります。
都市部だと……
- ネズミ
- ハクビシン
- アライグマ
- イタチ
といった動物が原因であるケースが多いと思います。
これらは床下に営巣することもあり、また断熱材や木材などもかじることがあるので、そういった場合にカリカリと音を出ことがあるわけです。
そもそも害獣って何なの? goo辞書で調べると、害獣とは…… 人間や家畜を襲ったり農作物を荒らしたりして、害を加えるけもの と書かれています。 また、獣とは…… 獣とは四つ足で歩く動物 と書かれております。 な[…]
床下からカリカリ音がするようになった場合はどうしたらいい?
基本的に害獣駆除業者を探すことを考えた方がよいです。
野生動物は、素人が簡単に対処できるものではなく、害獣駆除の知識やスキルを持っていない一般人が市販の道具などを買って自力で駆除しようとしても多くの場合無駄骨に終わるからです。
自力で駆除しようとしたことによる、時間とお金を無駄に浪費することになり、むしろ出費は増えることになる可能性が非常に高いのです。
それに、家ネズミであれば法律的には自前で駆除しても問題ないのですが、そのたの多くの動物の場合、法律的にもアウトになります。
なので、最初からきちんとプロに依頼することを念頭に動き始めるのが実はもっとも手っ取り早く確実に、なおかつ安価に害獣駆除被害に対策できるわけです。
頑張るならば、優良な業者を探すところを頑張った方が最良の結果を得られたりするわけです。
動物に住みつかれて駆除したいと思った時に読む記事 【結論】 きちんと『プロ』に依頼する 直接的なダメージを与えない『威嚇』 侵入経路が発見できた場合は『経路の遮断』 居ついた動物に合わせた『追い出し(いやがらせ)[…]
床下でカリカリ音がしたときの対処法は?
すでにご紹介したように一番確実に一番手早く問題解決できるのは『信用できるプロの害獣駆除業者に依頼すること』です。
でも、カリカリ音の主が家ネズミである場合は、下の様な対処方法で自力で駆除することもできます。家ネズミでない場合は、一般人が自力で駆除を行うことは法令的に問題になりますから、専門のプロ害獣駆除業者への相談一択です。
あと、重要なこととして、害獣被害への対処は駆除だけでは終わらず……
- 清掃
- 除菌・消毒
- 再発防止対策(侵入ルートの特定とブロック)
- 被害個所の修繕
- 害獣を捕獲した場合は、捕獲した害獣の処分
なども必要になるので、このあたりのことも失念しないようにしないといけません。
餌を取り除く
ネズミが出現する原因の一つは、食べ物が手軽に入手できる環境であることが挙げられます。そのため、家の周囲にあるゴミや食べ物の残りカスを徹底的に掃除し、食べ物を閉まっておくようにすることが大切です。
掃除を行う
ネズミは、ダニやノミなどの寄生虫を媒介することがあります。そのため、定期的に家や建物の中を掃除し、ネズミが潜む可能性のある場所を探して、清潔に保つことが大切です。
専用の罠を使用する
ネズミの駆除には、専用の罠を使用することが有効です。罠には、強い臭いのするチーズやピーナッツバターなどの食べ物を使用すると、ネズミが誘引されやすくなります。
毒餌を使用する
ネズミの駆除には、毒餌を使用することもあります。毒餌は、ネズミが食べると中毒症状が現れ、死に至ることがあります。しかし、毒餌は、ペットや小さな子供が手の届く場所に置かないように注意が必要です。
害獣駆除の相場は?悪徳業者にだまされるな! 【害獣駆除の相場】 1坪 2~3万円 1坪 1万円程度 だから…… 普通の家屋(20~30坪)なら10万円からの腹積もりで! 絶対必要なものを削る施工でもしない[…]
床下に巣を作る動物の繁殖期
やはり害獣被害は出産のために害獣たちが営巣する繁殖期にピークを迎えます。

ネズミは一年中活動しますが、繁殖期のピークはは春と秋の年2回。気温が上がり始めると繁殖活動が活発になります。寒さには弱い。ネズミは非常に繁殖力が強く、1匹のメスが年間に何度も出産することができるため、被害を受けないためには早期の対策が必要です。

繁殖期自体は冬ですが春に出産します。寒さに弱く、そのためより快適な環境を求めて床下などへ侵入してきます。

年明けくらいのまだ寒い時期から初春にかけて繁殖期を迎え、春から初夏にかけて出産します。

春半ばくらいから終わりにかけて繁殖期を迎え、そのあと1か月ほどで出産します。
床下の点検と予防対策の方法
床下からカリカリと音がする場合(特に生命感がある不規則な音のような場合)、害獣が原因である可能性が非常に高くなります。
どの害獣かはこの時点ではわかりませんが、生命感があるカリカリ音の場合はほぼほぼ害虫なり害獣なりの生物由来がかなり疑わしくなる訳です。
害獣は、家屋の下に侵入し、断熱材や配管、電気配線などを噛んで被害を与えることがあるので、そのときに音を出したりするのです。特に、ネズミやアライグマ、ハクビシンなどの害獣は、床下に穴を掘って巣を作ることがありますので、これらを念頭により詳しく調べていくと原因の判別がしやすくなります。
床下の点検をする際には、まずは安全に注意して行わないといけません。
床下に入る前に、ゴム手袋やマスク、長袖・長ズボンなどの防護具を着用し、明るい懐中電灯を用意します。また、床下に入る前に、周囲をよく見て、蜘蛛の巣やゴキブリのいる場所などを確認しましょう。
けがをする可能性。害獣などが原因だった場合、調べに行くと怯えた害獣の反撃にあったり、狭いところで点検作業を行っていてひっかけたりなどしてけがをすることもあります。
特に直接的に牙や爪でけがを負うことになると危険な病原菌を移されることもあるので最大限の注意が必要です。
また、直接的な攻撃以外でも乾燥して粉末状になっているフンを呼吸して吸い込んだり、フンを見つけて直接触ったりなどすると病原菌感染のリスクが大いに高まるので、マスク手袋などによる防御も忘れてはいけません。
基本、これらの調査も一般人にはなかなかハードルが高いので、最初にある程度の検討をつけるための自分自身の調査段階では、サッと見れる範囲で確認できる範囲にとどめて、なにがしかの害獣被害っぽいのが確認出来たらあとはプロに任せてしまうのが賢明です。
一応床下に入ってからの害獣の痕跡探しについても書いておきます。
害獣の痕跡としては、巣穴、糞、噛み跡、鳴き声などが代表的なものとして挙げられます。また、このときに配管や電気配線が噛まれているかどうかも確認します。配管や電気配線などの被害状況を確認しておかないと大きなトラブル(火事など)に繋がることもありますので、必ず行うようにした方がいいです。
そして、予防方法としては、床下にワイヤーネットを張ることが挙げられます。また、床下には害獣が侵入しにくいように補修したり、外部からの隙間をふさいで換気口や排水口などをワイヤーネットで塞いだりなどして駆除後新たに侵入できないようにすることも大事です。
いま現在害獣に住みつかれているということは、その場所は害獣にとって巣をつくるのに最適な環境になっている可能性が非常に高いということでもあります。
そのため、いま住んでいる害獣を捕獲したり追い出したりしても、また次が入ってくる可能性高いのです。それを防ぐためには、きちんと侵入経路を特定しあらかじめその侵入経路を塞いでおく必要があるわけです。
あと、食べ物の残りカスやゴミを片付けることも重要です。
害獣たちのエサになってしまいます。住み良い環境に加え食糧庫までそばにあれば、害獣たちにとっては天国みたいな環境になってしまいますので、そうなると『入居希望が殺到してしまう』わけです。
あくまでもざっくりとですが、これらが床下の点検方法と予防対策の基本となります。